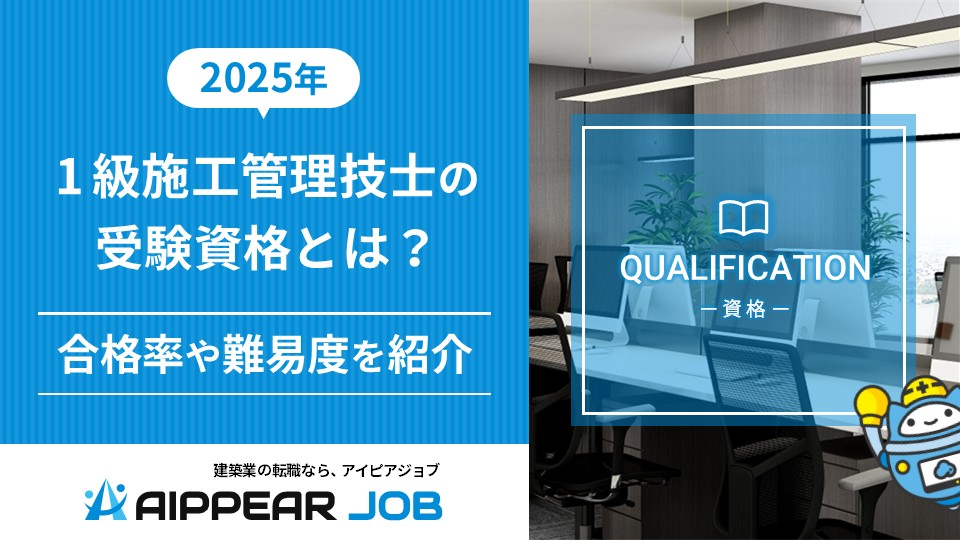建設業界では、品質の高い建設工事を安全かつ効率的に進めるためのプロフェッショナルが不可欠です。
その中核を担うのが1級施工管理技士という国家資格保持者です。
この資格は建設業界におけるキャリアアップの重要なステップであり、取得することで待遇や活躍の場が大きく広がります。
しかし、1級施工管理技士になるためには特定の受検資格を満たし、難易度の高い試験に合格する必要があります。
本記事では、2025年の1級施工管理技士試験における受検資格の詳細や、最新の合格率、試験の難易度について詳しく解説します。
資格取得を目指している方にとって、効率的な学習計画を立てる上での重要な情報となりますので、ぜひ参考にしてください。
1級施工管理技士とは
1級施工管理技士は、建設業界における重要な国家資格の一つです。
この資格は建設業法に基づいて定められており、高度な専門知識と技術を持った建設現場のプロフェッショナルであることを証明するものです。
建設工事の品質確保、安全管理、工程管理など、建設プロジェクト全体を管理・監督する能力を有することが認められた証となります。
1級施工管理技士の概要と役割
1級施工管理技士は、建設現場における最高レベルの施工管理者として位置づけられています。
建設工事の計画から竣工に至るまで、あらゆる段階で重要な役割を果たします。
具体的には、施工計画の立案と実行、品質管理、安全管理、工程管理、予算管理などを総合的に担当します。
また、現場での作業員の指導や関係者間の調整も重要な仕事です。
特に大規模な建設プロジェクトでは、工事現場に1級施工管理技士を配置することが法律で義務付けられているケースも多く、業界での需要は非常に高いです。
法令を遵守した適切な工事進行を確保する役割も担っており、建設業界の品質と安全の要となっています。
1級施工管理技士資格の種類
1級施工管理技士の資格は、工事の種類によって複数の区分に分かれています。
それぞれの区分は専門分野ごとの知識と技術を評価するもので、取得する区分によって活躍できる現場が異なります。
主な区分としては、建築工事、土木工事、電気工事、管工事、造園工事、建設機械施工、そして舗装工事の7種類があります。
それぞれの区分は試験内容も異なり、その専門分野における高度な技術と知識が求められます。
複数の区分を取得することで、より幅広い現場での活躍が可能になるため、キャリアの幅を広げたい方には複数区分の取得が推奨されます。
特に建築と土木の両方を持っている技術者は、総合建設会社(ゼネコン)などでの評価が高い傾向にあります。
1級と2級の違い
施工管理技士には1級と2級があり、その違いは責任の範囲と求められる技術レベルにあります。
1級施工管理技士は、より大規模で複雑な工事の管理を任されるのに対し、2級施工管理技士は比較的小規模な工事や1級の補佐的な役割を担当します。
具体的な違いとして、1級は受検資格に必要な実務経験年数が長く設定されており、試験の難易度も高いです。
また、法律上の扱いも異なり、一定規模以上の工事では必ず1級施工管理技士の配置が義務付けられています。
給与面でも1級取得者は優遇されることが多く、キャリアアップを目指す方にとっては1級取得が重要なステップとなります。
2級から始めて実務経験を積みながら1級を目指すというキャリアパスが一般的です。
| 1級施工管理技士 | 2級施工管理技士 | |
|---|---|---|
| 担当工事規模 | 大規模・複雑な工事 | 中小規模の工事 |
| 必要実務経験 | 3〜10年(学歴による) | 1〜8年(学歴による) |
| 試験難易度 | 高い(合格率約15〜30%) | 中程度(合格率約30〜40%) |
| 給与水準 | 高い | 標準的 |
建築・土木専門職に関する記事はこちら
1級施工管理技士の受検資格と必要な実務経験(2025年度最新版)
1級施工管理技士試験は、建設業界における重要な国家資格の一つです。2024年度から受検制度が大きく改正され、2025年度試験もこの新制度に基づいて実施されます。 新しい受検制度では、受検者の選択肢が広がり、より多様なルートで1級施工管理技士を目指せるようになりました。
2025年以降の受検制度のポイント
1級施工管理技士試験は、第一次検定(学科)と第二次検定(実地)の2つの試験で構成されます。 それぞれの検定には受検資格がありますが、2024年度からの制度改正により、第一次検定に関しては大幅な緩和が行われました。
第一次検定の受検資格
第一次検定(学科)については、
- 19歳以上であれば誰でも受検可能
- 学歴や実務経験の有無は問われません
これにより、建設業に未経験であっても、若年層を含む幅広い人材が受検できるようになっています。
第二次検定の受検資格
第二次検定(実地)を受検験するためには、以下の条件を満たす必要があります:
- 第一次検定に合格していること(※1級施工管理技士補の称号が付与されます)
- 一定の実務経験があること
実務経験とは、工程管理、品質管理、安全管理、原価管理など、建設工事の管理業務に直接関与した期間を指します。
実務経験の要件
第二次検定では、下記のいずれかのルートで実務経験年数を満たしている必要があります:
- 建設業での施工管理業務の経験が5年以上
- 建設業での施工管理業務が3年以上で、かつ「監理技術者補佐」「主任技術者補佐」「技術士補」などに関する追加要件を満たす者
- 建設キャリアアップシステム(CCUS)登録の監理技術者補佐としての経験が1年以上
これらの条件に該当する場合、第二次検定を受検することができます。
※上記のルート以外にも、一部経過措置(旧制度)に基づく受検が可能です。
旧制度(経過措置)について
2024年度から制度が改正されましたが、令和10年度(2038年度)までは旧制度に基づく受検も認められています。
旧制度の要件(学歴別の必要な実務経験年数)は以下の通りです
- 大学の指定学科卒業:3年以上
- 短期大学・高等専門学校の指定学科卒業:5年以上
- 高等学校の指定学科卒業:7年以上
- その他(指定学科以外の卒業者や高卒未満):10年以上
この旧制度のルートでも、要件を満たしていれば受検可能です。
指定学科とは、建築学、土木工学、電気工学など、受検する区分に関連する学科を指します。
指定学科でない場合は、より長い実務経験が必要になりますので注意が必要です。
特例措置と免除制度
1級施工管理技士試験には、一定の条件を満たす受検者を対象とした特例措置や一部科目の免除制度があります。
これらの制度を活用することで、試験の負担を軽減できる可能性があります。
第一次検定合格者の免除制度
- 第一次検定(学科試験)に合格した場合、その合格は5年間有効。
- その期間中は第二次検定(実地)のみの受検で済みます。
2級施工管理技士を取得済みの方
- 第一次検定(学科試験)の内容に一部共通点があるため、学習面で有利になります(科目免除はなし)。
他資格保有者の免除制度:
- 技術士など他の国家資格を保有している場合、所定の条件を満たせば一部試験科目の免除が適用される場合があります。
1級施工管理技士試験の内容と合格率
1級施工管理技士試験は、建設業における高度な施工管理能力を証明する国家資格であり、難易度の高い試験です。試験内容の理解と合格率の傾向を把握することで、より効果的な学習計画を立てることができます。ここでは試験の構成、出題内容、合格率、学習方法について解説します。
試験の構成と出題内容
1級施工管理技士試験は、第一次検定(学科試験)と第二次検定(実地試験)の2段階で構成されています。
両方の試験に合格して初めて資格取得となるため、それぞれの試験内容を理解しておくことが重要です。
第一次検定(学科試験)は、主に施工管理に関する理論や知識を問う試験で、マークシート方式により実施されます。
出題内容は「施工管理法」「建設工事の目的・内容」「施工計画」「工程管理」「品質管理」「安全管理」「建設機械」「法規」などの分野からバランスよく出題されます。
一方、第二次検定(実地試験)は実務能力を評価する記述式の試験です。
実際の現場で直面する問題に対する解決策や、施工計画の立案など、より実践的な内容が問われます。
両試験とも合格基準は60%以上の正答率ですが、第二次検定(実地試験)は採点基準が厳しく、特に記述力や論理的な思考力が問われます。
直近の合格率と難易度分析
1級施工管理技士試験の合格率は、年度や専門区分によって若干の差はありますが、総じて厳しい水準となっています。
直近のデータを見ると、第一次検定(学科試験)の合格率は約30%前後、第二次検定(実地試験)は約40%前後で推移しており、両方合わせた最終的な合格率は20%程度となっています。
区分別に見ると、建築施工管理と土木施工管理が受検者数も多く競争率が高い傾向にある一方、管工事や造園工事など専門性の高い区分は受検者数は少ないものの、求められる専門知識のレベルが高いという特徴があります。
特に第二次検定(実地試験)では、実務経験の少ない受検者にとっては難易度が高く、現場での実践的な知識が問われる問題が多く出題されます。
2025年の試験においても同様の傾向が続くと予想されますが、近年は働き方改革や技術革新を反映した問題も増えているため、最新の動向にも注意を払う必要があります。
| 第一次検定(学科) | 第二次検定(実地) | 最終合格率 | |
|---|---|---|---|
| 建築施工管理 | 約30-35% | 約35-40% | 約15-20% |
| 土木施工管理 | 約35-40% | 約40-45% | 約20-25% |
| 電気工事施工管理 | 約30-35% | 約40-45% | 約20-25% |
| 管工事施工管理 | 約30-35% | 約35-40% | 約15-20% |
引用
効果的な学習方法
1級施工管理技士試験に合格するためには、計画的かつ効率的な学習が不可欠です。
多くの合格者が実践している効果的な学習方法を紹介します。
まず最も基本的なのは、過去問題の徹底的な分析と理解です。
過去問は出題傾向や難易度を把握するための最良の教材であり、特に頻出テーマについては確実に理解しておくことが重要です。
次に、専門書籍や参考書を使った体系的な学習も効果的です。
基礎理論から最新の施工技術まで幅広く学ぶことで、試験での応用力も身につきます。
多くの受検者が利用しているのが、通信講座や予備校などの専門的な学習サポートサービスです。
これらは効率的なカリキュラムと質の高い教材で、限られた時間で最大の効果を得ることができます。
また、第二次検定(実地試験)対策としては、実際に記述問題を時間を測って解く練習が必須です。
現場での経験を言語化する訓練も重要で、日頃から施工管理の視点で現場を観察する習慣をつけることで、実践的な知識が身につきます。
1級施工管理技士資格取得後のキャリアと待遇
1級施工管理技士の資格を取得することは、建設業界でのキャリアに大きな影響をもたらします。
高い専門性と責任ある立場が認められ、様々な面でのキャリアアップが期待できます。
ここでは、資格取得後の具体的なキャリアパスや待遇について詳しく見ていきましょう。
資格取得によるキャリアの可能性
1級施工管理技士の資格を取得すると、建設業界内での幅広いキャリアパスが開けます。
まず最も一般的なのは、建設会社内でのキャリアアップです。
現場監督から工事責任者、さらには現場所長や工事部長などの管理職へと昇進していくケースが多く見られます。
特に大規模プロジェクトの責任者となるためには、1級施工管理技士の資格が必須条件となっていることが一般的です。
また、ゼネコンのみならず、専門工事会社やコンサルティング会社、さらには官公庁の技術職員など、活躍の場は多岐にわたります。
近年では建設業界の技術者不足を背景に、資格保有者への需要が高まっており、転職市場でも高い評価を受けています。
さらに、独立して施工管理の専門家として活動する道も開かれています。
個人事業主として複数の現場を掛け持ちする「現場監督代行」や、建設コンサルタントとして活動するケースも増えています。
資格取得後の給与や待遇の変化
1級施工管理技士の資格取得は、給与や待遇面でも大きなメリットをもたらします。
多くの建設会社では、資格取得に伴う資格手当や昇給が設定されています。
一般的に資格手当は月額2万円から5万円程度が相場となっていますが、会社規模や地域によって差があります。
大手ゼネコンなどでは、より高額の手当が支給されるケースも少なくありません。
また、基本給そのものも資格取得を契機に見直されることが多く、年収ベースで50万円から100万円程度のアップが期待できます。
特に複数の区分の1級資格を保有している場合は、さらに高い評価を受けることになります。
資格取得者は法的にも一定の地位が保証されており、建設業の許可申請時の専任技術者や、監理技術者として現場に配置されることで、その専門性が正当に評価される仕組みになっています。
建設会社にとっても資格保有者の存在は重要であるため、資格取得を奨励する社内制度を設けている企業も多いです。
継続教育と更なるステップアップ
1級施工管理技士の資格取得はゴールではなく、継続的な学習と専門性の向上が求められます。
建設技術は日々進化しており、最新の知識や技術を常にアップデートしていく必要があります。
多くの場合、CPD(継続教育)制度への参加が推奨されており、セミナーや講習会への参加、専門誌の購読などを通じて専門知識を更新していきます。
これらの継続教育の実績は、キャリアアップや評価にも反映されます。
さらに上のステップとしては、技術士や一級建築士などの上位資格への挑戦も選択肢となります。
特に技術士(建設部門)は施工管理技士の上位資格として位置づけられており、さらに専門性の高い業務に関わる機会が広がります。
また、BIM(Building Information Modeling)やCIM(Construction Information Modeling)などの先端技術に関する知識やスキルを身につけることも、今後のキャリア発展において大きなアドバンテージとなるでしょう。
建設業界のデジタル化が進む中、従来の施工管理のスキルに加えて、これらの新技術に精通した人材の需要は今後ますます高まると予想されています。
建築業の転職ならAIPPEAR JOB(アイピアジョブ)

AIPPEAR JOB(アイピアジョブ)は、
建築業界に特化した転職支援サービスです。
無料オンライン相談や企業とのマッチングを通じて、建築業の転職活動を行えます。
従来の求人サイトとは異なり、スタッフのサポートのもと、スキルや経験、希望条件から精度の高いマッチングを行うため、効率的な転職活動が可能です。
アイピアジョブの6つの特長
- 築業界に特化した優良求人で、
労働環境の整ったホワイト企業に出会える - 安心の1on1サポートで最適な企業との
出会いを実現 - 無料オンライン相談で
転職の希望や悩みを丁寧にヒアリング - 求職者の「働く価値観」にマッチした職場をご紹介
- 求人検索や企業との面接の日程調整など、
転職活動に必要な手続きを代行 - エージェントとの連絡は全てLINEで完結
まとめ
1級施工管理技士は建設業界における重要な国家資格であり、取得することで様々なキャリアの可能性が広がります。
2025年の試験に向けては、受検資格となる実務経験や学歴要件を確認し、計画的な準備が必要です。
受検資格は学歴によって必要な実務経験年数が異なり、大学の指定学科卒で3年、高校の指定学科卒で7年など、教育背景に応じた条件が設定されています。
試験自体は第一次検定(学科試験)と第二次検定(実地試験)の2段階で構成され、合格率は約20%前後と難易度の高い試験です。
効果的な学習のためには、過去問分析や専門書籍の活用、さらには通信講座の利用など、自分に合った方法を選択することが重要です。
資格取得後は、給与アップや昇進、さらには活躍の場の拡大など多くのメリットが期待できます。
建設業界で長期的なキャリアを築きたい方や、現在の立場からさらなるステップアップを目指す方にとって、1級施工管理技士の資格取得は非常に価値のある挑戦です。
本記事の情報を参考に、効率的な学習計画を立て、資格取得への道を着実に進んでいただければ幸いです。
建築・土木の資格に関連する記事はこちら
- 2級建築士の受験資格とは?合格率や難易度を紹介
- 2級建築士の「製図試験」独学は無理?概要や勉強方法を紹介
- 1級建築士になるには?必要な学歴や実務経験を紹介
- 1級建築士の受験資格とは?合格率や難易度を紹介
建築・土木に関する記事はこちら